


教育講演
「家族のメンタルケア」
佐伯 俊成
(広島大学大学院 総合診療医学)
患者本人の良好な心理社会的適応にとって,その家族の心理状態,夫婦関係,家族機能などの要因が重要な役割を果たすことはさまざまな疾患において観察されており,医療システムには患者のみならず家族をも対象とした心理社会的介入プログラムが盛り込まれることが望ましい。
しかしながら日本の医療においては,家族は患者支援の重要な担い手として位置づけられ,家族の被る心理的苦痛は見過ごされ,過小評価されやすく,家族に対する実証的根拠のある介入プログラムは今のところ皆無である。
こうした現状から,ここではまず医療ユーザー1000人アンケート調査の結果などを基に,医療における家族のメンタルケアとは何か,そして家族のメンタルケアは誰が行うべきであるのか,について概説するとともに,一般診療科のスタッフが知っておくべき家族のメンタルケアの基本技術についても提言する。






講 演
「先端医療における
ホリスティック・ケア
−リエゾン精神専門
看護師の立場から−」
野末聖香
(慶應義塾大学 看護医療学部)
先端医療において、患者、家族、医療者の期待と不安、葛藤は極めて大きいものである。患者は、病気と予後、治療内容、治癒の可能性とリスクについて説明を受け、治療をするかしないかを選択する。希望を託して治療を受け、その結果に喜んだり失望したりする。いずれの段階においても、患者は重いこころの作業を身体的な苦痛を抱えながら行っている。看護師は、患者の身体的苦痛を癒し、生活行動を支援することを通してこころのケアを行う。このプロセスにおいては、患者の精神状態・身体状態を査定し、治療によって生じる身体的変化や苦痛の予測のもとにケアすることが必要である。そのために看護の専門性を高めることが必須であり、当該先端医療分野を専門とする看護師やリエゾン精神専門看護師が活動している。看護の専門性を高めることと同時に重要なことは、精神科医や臨床心理士などこころの専門家との連携である。お互いの役割を理解し、実際的な役割分担と協働のシステムづくりを検討することが必要である。
シンポジウム
『サイコセラピーはいかに最先端医療に貢献するか』
「HIV/エイズが問いかける
古くて新しいテーマ」
矢永由里子
(財団法人エイズ予防財団)
HIV感染症は比較的新しい疾患で、この疾患の治療が本格的に日本で始まったのは1990年代初頭です。その後97年ごろより薬剤の開発が格段に進み、現在は約20種類の薬剤使用が可能です。短期間にこれ程治療が進歩した疾患はこれまでなかったと思います。しかし、HIV感染症が持つ心理社会的課題は、日本のこれまでの感染症に共通するもので、最も根強い課題は人々の偏見(スティグマ)です。疾患の治療が改善されても疾患への理解が進まない限り、人々のHIVの受け入れは難しく、引いては、患者がHIV感染した身体と感染から生じる様々な心理社会的な問題に対峙することが一層困難になります。HIV感染によって周囲との絆の突然の分断というトラウマを経験する感染者に対し、対人関係の再構築やHIV感染症を身体疾患のひとつとして受け入れていく過程への支援が心理臨床のスタートになります。また、人間の性というテーマがHIV感染症に密接に関係します。人が生き、愛し、死んでいくという存在の根本のところをしっかり見据えていくことも心理臨床に求められていると言えます。
「遺伝カウンセリング」
斎藤加代子
(東京女子医科大学附属
遺伝子医療センター)
ゲノム解析が進み、遺伝学的検査は、疾患の診断、薬の副作用の予測、さらに体質検査まで広く発展しつつある。遺伝情報は、遺伝的疾病体質を予見し得ること、世代を越えて子孫を含めた家族に対して、集団全体に対して重大な影響を有し得ること、生物学的試料の収集の時点では必ずしも知られていない情報を含み得ること、そして個人または集団に対する文化的な重要性を有し得ることが特徴である。本人のニーズに対応して遺伝学的情報など適切な情報を提供し、本人と家族がその内容を理解した上で意思決定できるよう支援することが遺伝カウンセリングのプロセスである。本人・家族の医学的・心理的・社会的支援をチーム医療として実施することが遺伝カウンセリングの望ましい方向性として考えられる。全ゲノムの解明という急速な遺伝子医学の進歩、わが国の医療事情、倫理的問題にも対処でき、オーダーメード医療にも対応できる人材の育成が必要である。
「揺れるこころに寄り添う:
がん医療におけるサイコセラピー」
栗原幸江
(静岡がんセンター 緩和医療科)
がんとの闘病の道のりにはいくつもの「荒波」や「険しい山」が散在する。診断時、抗がん治療中、治療後、再発・転移時、抗がん治療中止時など、数々の「山場」において、闘病に伴う不安や数々の喪失の悲嘆、自責の念、そうしたつらさを語れない・わかってもらえない孤独感や孤立感―こうしたこころの揺らぎを患者の誰もが経験する。またその患者の伴走者役を担う家族も、同様の「山場」にいくつも向き合っている。
がん医療の現場では、患者・家族を多職種からなるチームがサポートする。こころの安寧が治療意欲や生きる意欲を支えるということを理解しているからこそ、こころも身体も大切にする多職種の専門家の視点やスキルの総合力が求められるのである。
揺れるこころに寄り添うところから「いのちをテーマとした対話」が生まれ、対話を通じてその人自身の内に確かに存在する「力」をその人自身が体感する―そこに、サイコセラピーがもたらす「抱え」があると思う。事例なども交えながら、チーム医療の中の心理療法士の役割、そしてがん緩和医療の現場におけるサイコセラピーの展開についてお話ししたい。
特別講演
「サイコセラピーと
メンタライゼーション」
狩野力八郎
(東京国際大学大学院 臨床心理研究科)
心身医学は、F.アレクサンダーらが精神分析的思考を医学一般に適用する試みによって誕生した。当時の彼らにとって、メインテーマは「心と身体のmysterious leap」であった。その後、心身医学の普遍化と停滞に直面するなかで、アレクサンダーらに続く次の世代の力動精神科医(あるいは精神分析的方向付けを持った臨床家)たちが、切り開いた地平がコンサルテーション・リエゾン精神医学であった。それは、心身医学における全体としての人間という、いわば「個人」的視点を超えて、さまざまな臨床場面で展開するさまざまな治療関係すなわち「関係性」の意義を強調したという意味において新鮮であった。これは、医療における心理療法にナラティヴの視点を導入した英国のM,バリントの活動、フランス精神分析の伝統的な身体性への注目、ドイツの新しい心身医学なども含む国際的な動向へと展開したが、それらを進化させた新しい形態の心理療法がメンタライゼーションにもとづく心理療法である。
特別講演
「患者さんの話を聞くことの
大切さと意味」
春木繁一
(松江青葉クリニック)
慢性で治癒しにくい病気の患者さんは、「とにかく自分の話を聞いて欲しい」と思っている。まずは、この希望をかなえてあげることである。話を聞いていく中で、
1)この患者さんは人生のいかなる時期にこうい
う病気になったのか
2)病気になることでどういうものを失ったのか
3)これまでの「病人」としての歴史
4)その人のこれまでの人生
5)今、患者さんが自分の状態をどう思っている
か―重症と思っているのか、大丈夫と思ってい
るのか
6)「なぜ、今自分だけがこのようなこと(病気)
にならないといけないのか」という気持ちにつ
いて、こちらがどこまで汲み取ってあげられる
かが相手にとって意外に大きい「セラピー」に
なるであろう。
教育講演
「医療従事者の
メンタルヘルスケア
―自称サイコセラピストの憂うつ―」
佐野 信也
(防衛医科大学校 心理学・精神科)
演者は,保険診療体制に基づく大学病院及び単科精神科クリニックで,とくに診断や病態を限らずに診療を続けてきた。病態を選別しないといっても,同じ場所で診療を続けていると,学問的関心,仕事上の付き合いの範囲や治療者自身の個性により,治療継続患者の診断や病態には相応の濃淡が生じてくるものである。演者の場合は神経症圏患者一般や,地域保健機関や児童相談所からの紹介を受けての,子どもの虐待や種々の心的外傷に関連する当事者あるいはその家族が診療対象のかなりの比重を占めるに至っている。与えられた主題は「医療従事者のメンタルヘルス」であるので,医療福祉関係職種者の「燃えつき現象」に関する研究史の概略を紹介した上で,特定の流派や職種によらず,精神療法を担当する者とそれを内外から支える多職種者(臨床心理士,ソーシャル・ワーカー,保健師,教師,各科医師等)の被る心理的ストレスについて,演者自身の経験を頼りにお話したい。

会長講演
「PTSDの薬物療法」
外傷後ストレス障害(PTSD)は、その発症の引き金となったイベントが明確であり、かつ特徴的な症状群を呈することから、ストレス関連障害の一つのモデルと考えられる。また、その病態は記憶と情動の障害であると考えられることから、精神療法と生物学的治療の双方からのアプローチが必要であり、かつこの両者を包括的に統合した治療理論を組みたてていくことが望まれる。
PTSDに対する薬物療法を検討した報告はいくつかみられる。しかし、有効性を検証する試験デザインやエンドポイントの設定法については一定のものがなく、結果の解釈は必ずしも容易ではない現状であることに留意しておかなければならない。今日もっとも広く有効性が認められているのは抗うつ薬であり、とくに選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)は一定レベルの有効性が期待できる治療薬である。このほか、古典的な三環系抗うつ薬も、副作用の問題はあるが、有効性は認められている。このほか、いくつかの薬物に関する報告があり、本講演ではこれらのデータを概観したうえで、現在考えられる標準的な薬物療法について考察したい。
野末 聖香「先端医療におけるホリスティック・ケア
−リエゾン精神専門看護師の立場から−」
斎藤加代子「遺伝カウンセリング」
矢永由里子「HIV/エイズが問いかける古くて新しいテーマ」
シンポジウム 栗原 幸江「揺れるこころに寄り添う:
がん医療におけるサイコセラピー」
狩野力八郎「サイコセラピーとメンタライゼーション」
特別講演 春木 繁一「患者さんの話を聞くことの大切さと意味」
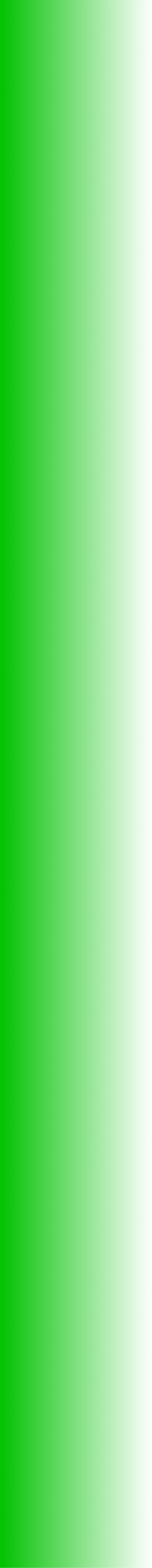
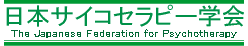
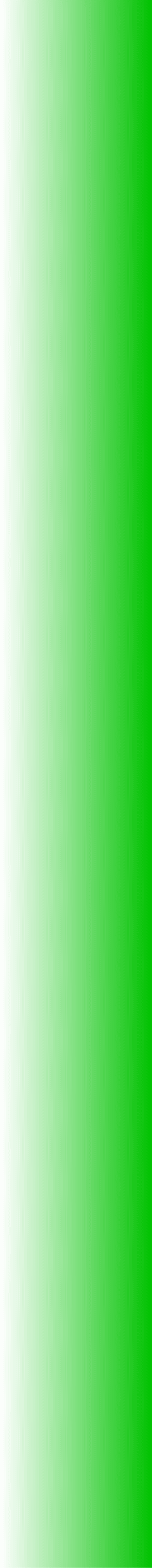
佐野 信也 「医療従事者のメンタルヘルスケア
―自称サイコセラピストの憂うつ―」
第10回日本サイコセラピー学会 学会抄録
会長講演 石郷岡 純「PTSDの薬物療法」
教育講演 佐伯 俊成「家族のメンタルケア」